高坂氏館跡・野本氏館跡 散策 参考地形図 東松山
令和5年(2023)7月4日 晴れ
1.高坂氏館跡 埼玉県東松山市高坂
遺構は高済寺境内西に土塁・堀が僅かに残る。北と東は崖状の段差を要害としている。説明板の概要は、南北朝時代に高坂氏の居館として造られた。高済寺から南にある子育て支援センター周辺の発掘調査では、高坂氏の活躍した時代(14世紀前半)のかわらけ・輸入陶磁器が出土しており、館の中心地は南にあった可能性がある。
伊勢宗瑞が明応3年(1494)、北条氏康が永禄5年(1562)にそれぞれ在陣。発掘調査では土塁・堀の改修が見られ、戦国期に整備されたと推定される・・・等々。土塁北上には加賀爪氏累代の墓があり、江戸時代初めに加賀爪氏が陣営を設けるが、天和元年(1681)に改易と説明がある。
山門左に土塁が残存する。境内左に城山稲荷、土塁の北端に加賀爪氏の墓地がある。土塁に上る階段を見ると境内からの高低差具合が分かる。
  
  
西には残存土塁と堀を見ることが出来る。堀の南は埋められ駐車場になっている。八王子・日光道が松山方面に抜ける「高坂の渡し場」の手前の水路に石橋が架けられていた・・・。と書かれている。
  
| 台地下から、堀の末端を |
台地下の一風景 |
石橋と石橋供養塔(右奥) |
  
2.野本氏館跡 埼玉県東松山市下野本
説明板に拠ると、平安時代の公卿藤原家の警護をしていた片品基親の子、基員が武蔵国野本に移り野本氏を名乗ったが始まりと言われる。館跡は現在、無量寿寺の境内になっており、本堂北裏に土塁と堀が僅かに認められる。実際には二重の土塁・堀が廻っていたが、これは後世の増築と考えられる。
館の造られた時期は、貞永元年(1232)に基員が亡くなったこと、無量寿寺に残る建長6年(1254)銘の銅鐘の拓本より、当時無量寿寺が野本寺と呼ばれていたとあり、遅くとも十三世紀初頭には造られたと考えられる。
道を挟んで南には前方後円墳の将軍塚古墳があり、後円頂部に利仁神社が祀られている。案内板の通り遺構は本堂裏に短い土塁、堀と思われる僅かな凹みが竹藪内にある。西側一帯は墓地になる。
| 前方部近くの忠魂碑 |
活動センター東の鳥居 |
後円部の二段先に社殿 |
  
| 利仁神社 |
古墳西の道路、先に寺 |
無量寿寺から将軍塚古墳 |
  
  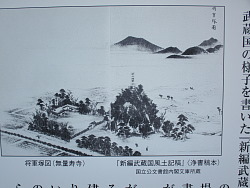
  
|