| 甲子山(1549 m) 三角点なし 西白河郡西郷村/南会津郡下郷町 平成16年(2004)8月17日(火)曇/雨 参考地形図 甲子山 甲子山は福島県下にあり、私のホームページ・那須周辺に似合わないが、三本槍岳などとの縦走コースがよく紹介されているため入れてみました。前日に甲子温泉まで入り旅館・大黒屋に宿泊する。   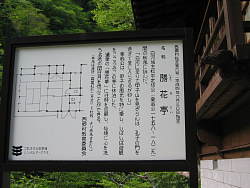 甲子山と旭岳へ行こうと予定しているが、天気予報では17日から曇りのち雨になるとのこと。雨なら甲子山だけで降りてこようと思いつつ歩き出す。旅館の敷地西にある離れ(勝花亭)の屋根下を潜り国道289号と標識のある狭い道を歩き出す。左手から流れ落ちる本沢を渡ると本格的な登山道となる。白水の滝に向って道を左に取ると、数分で温泉神社の階段下を通過する。回り込むように登ると神社の左脇にでる。そのすこし先が衣紋滝との分岐点になる。左折し甲子山方面に行くと左奥に建物が見え出すが、これは橋を造っている現場らしい。そう言えば新甲子から新しい道路が出来ている。(もちろん今は通れないが。)徐々に九十九折りの連続となる。    地図で見ても猿ヶ鼻まではかなりの急登だが、折り返しで上って行くのでさほど苦痛ではないのが幸いだ。周囲は阿武隈川減流域としてブナ等の原生林が多いとあったが、確かにそのようだ。折り返しが少なくなり真っ直ぐになってくるとすぐに猿ヶ鼻に着く。植生も変わっており、シャクナゲなどが点在する。ここからはあまり高低差が無く登り、30分程度で甲子峠との分岐に到着。   先は表面の土が流され石(岩かな)が露出しており滑りやすそうだが、ロープはしっかり張ってある。道の両脇には曇りのためか、早いのか、花を開いていないが意外にリンドウが多くあった。山頂近くから振り返ると西郷方面が眺められ、左後方には三本槍岳、左手には旭岳の山容が見え出す。すぐに木々で隠れてしまうが山頂はあっと言う間である。山頂は登ってきた東の展望こそないが、その他の眺めは良い。しかし直に東からガスが上がってきて、旭岳を隠してしまう。それでも数分も経つとまたガスが切れたりと断続的だ。大白森山・下郷町側はガスがかからず見渡せるがこちら方面も時間の問題か。見えても空は雲が多く、どんよりしてすっきりしない。晴れていれば目の前に迫る旭岳はさらに迫力が増すと思う。ガスの切れることと、若干の眺めを期待しながら旭岳に向かう。       下り始めた場所にもリンドウがあり、猿ヶ鼻側と同じく他の花々は少ない。下るにつれて木々は高くなり、曇り空と相まって一層暗く感じられる。鞍部では直進と左折とに道が分かれる。ここでは便宜上旧道・新道としておくが、分かれると言っても直進の旧道は一応足下に木の枝で行かないように注意を呼びかけている。現在は使用されていないようだが、旅館でもらった案内図には両方が記載されている。ここは旭岳に向かうため迷わず直進する。しばらくして雨が降り出してかなり強く、ザック・ズボン・シャツなどがあっと言う間にびしょぬれになってしまう。急ぎレインウェアーを着用。旧道は100メートル位の間は十分に踏み跡を見られるが、徐々に笹が多くなり道筋を隠している。笹の高さも上りではあるが胸下まである。笹をかき分けなければ踏み後が確認できず、石・木の根につまずきやすい。水のみ場(と、あったと思う)の標識があるが、場所の確認はしなかった。笹などの雰囲気からして右にやや下ったあたりだろうか。旭岳との分岐になるがここでも旭岳側には注意の印がある。雨が止む気配がなく旭岳に行くかどうかで足が止まってしまった。当然行っても周囲は見ないだろうし、レインウェアーを着てじっとしているのではおもしろみがない。ここで引き返すには若干時間が早いため、とりあえず坊主沼まで足を延ばすことにした。 しかしここからが一苦労だった。笹は一層ひどくなり必死にかき分けて進むようになった。所々には赤テープもあって迷うようなことはないが、旭岳分岐からしばらくして幅が10メートルほど崩れている場所に出る。上から岩などが崩れてきたようだ。大げさに言うとここは進む道筋を見失いかねないくらい整備されてない。地形図の1630メートル地点辺りへ来ると木々の高さが低くなり、明るい雰囲気で歩ける。しかも雨が止んでガスも切れ始め、右手上には旭岳が手が届きそうに見える。これなら旭岳に無理をしてでも行っておけばと、やや後悔したが後の祭りである。しかし今更引き返して行くだけの時間に余裕はなく、坊主沼へ行くしかない。下り始めてまもなく先の方に小さく赤い屋根の避難小屋とその奥に坊主沼の水面がわずかに見える。下りきると小屋の10メートル手前で新道が左手から合流してくる。    避難小屋は正面が広い板敷きで5〜6人寝られそうで、両側も腰掛け程度の幅ながら横になろうとすればなれる。中央は火を使えるように作ってあるが、暖を取るためのもののようだが、コンビニなどの袋に入ったゴミが放置してある。泊まりか立ち寄った者かは分からないが、ゴミを置いていくのはどうかと思う。以前から耳にしていたノートが置いてある。好きなことを書いていいノートで、2003年から結構書いてあった。記入者は縦走中に泊まった人、通過で休憩した人などと色々だが、殆どはここまでの行程の感想が多かった。中には登山道の整備が悪いから整備をしてほしいとか、旭岳側の道に入ってしまう可能性があるため、どうにかしてください等と書いたものもある。沼越しに見上げる旭岳もなかなかいい。今は緑一色だが、紅葉の時季にはどのような感じか。写真を何枚か撮っているうちに周囲にガスがかかり始めてきた。ガスは沼を幻想的にし、これはこれでいい雰囲気ではある。旅館で作ってもらった握り飯で腹ごしらえをする。    戻りは新道を使ったが、旧道と比べ高低差なくよく整備されている。上の道には沢は見あたらなかったが、この道はいくつもの沢(一跨ぎのような幅)があるので、最悪の場合には水の確保が出来る。すっかりガスに霞んで視界は20メートルくらいなものか、甲子山への登りにかかっても視界は殆ど変わらず。甲子山に着いた時点では雨は降ってないものの周囲は全く見えない。そのまま素通りし下山。登って来るときに、露出した石(岩)が滑るのではと思ったが、滑るようなこともなく何ら問題はなかった。猿ヶ鼻を過ぎたあたりから雨が落ちてきた。しかし大木が空を覆っているため濡れる事はない。行きに寄らなかった白水の滝に寄ってみた。高さ15メートル程の滝あるが、その一段上の砂防ダムが目に入り景色としての邪魔をしている。 従業員の話では、やはり秋の紅葉が一番とのこと。那須周辺は一般的に紅葉が早いのだが、ここは約1000メートルの標高であり、予約も10月の中旬から下旬にかけての土・日はかなり埋まってきているらしい。 時間のかかりすぎで参考にはならないが、載せてみました。 大黒屋 6:17(1.34 途中15分休憩)7:51 猿ヶ鼻 8:01(0.31)8:32 甲子峠分岐 8:32(0.31)9:03 甲子山 9:40(0.38)10:02 鞍部分岐 10:02(1.32 途中20分休憩)11:40 坊主沼 12:30(0.31)13:01 鞍部分岐 13:01(0.29)13:30 甲子山 13:55(0.13)14:08 甲子峠分岐 14:08(0.21)14:29 猿ヶ鼻 14:29 (0.57) 15:26 大黒屋 |